築上町有機液肥製造施設|農家と町民を支える循環型農業のかたち【福岡県築上町】

「地球の資源は限られている」「SDGsで環境問題に取り組む」。
よく耳にする言葉ですが、なんとなくふわっとした印象でしか捉えたことがない方は多いのではないでしょうか。
「農業」という分野でいうと、植物を育てるために必要な肥料の多くは現在「化学肥料」が使われています。化学肥料の製造には化石燃料や鉱物資源が必要なため、いつかはこれらの資源が尽きてしまいます。
また、日本は化学肥料を輸入していますが、最近は輸入自体が戦争によって困難になっています。

そんななか、化学肥料に頼らない農業を推進している福岡県築上町。
今回はそんな築上町の循環型農業について直接取材してきました!
築上町が行う循環型農業とは

訪れたのは「築上町有機液肥製造施設」。
「し尿処理のためにコストがかかるなら、有効活用できる仕組みを選ぼう」という当時の町長の取り組みから、この施設が出来ました。

ここでは、町の住宅や施設から“し尿(尿や便)”や浄化槽汚泥を集め、液肥にしています。
その液肥を町が田畑に散布する→作物ができる→それを食事として食べる→し尿になる→それらを集めて再び液肥にする

これが築上町の「循環型農業」の仕組みです。
なんと、町内から集められ液肥化された“し尿”は、その全てが農家さんに有効活用されているという100%循環をかなえています。
廃棄物として処理するより、資源として液肥にし、さらに農家さんに代わって町が液肥を農地に散布することで農家は生産コストを下げることができ、町はし尿処理にかかるお金を節約することができます。
なぜ築上町は成功しているの?循環型農業の難しさ

ここまでを読んでいると「それが環境にいいなら、どの町でもそうすればいいのでは?」なんて疑問が浮かんできませんか?
この取り組みを他の地域でもやってみようと思っても、そう簡単なことではありません。築上町にはその成功の難しさを感じながら地道にコツコツと積み上げてきた人たちがいました。
大切なのは、農家の視点に立つこと
「そもそも、どうして他の地域でこの形が発展していないんでしょうか?」
築上町の循環事業を立ち上げた時から、第一線で活躍してきた下田参事にお伺いしてみました。

「普通は、まずこの液肥を使ってくれる農家がいないだろうね。」
通常は、農家さん自身で使用する肥料を決める農業。行政から「町でし尿を使って液肥を作ったからこれを使ってください」と言っても、農家さんにとっては、数ある肥料の中の1商品にすぎません。
事業開始当時、下田参事は、「町で作った液肥を使うからといって、化学肥料に比べて作物が大きく育ったり、収穫量が増えたり、そういった特別なことはないです。」と農家さんに正直な前提をお話ししました。

その上で、液肥は町が作るため肥料代が節約できることや、散布作業自体も町が行うため人件費が削減できることなど、農家さんの日々の作業の大変さを担ってくれるメリットがあると売り込みを続けたそうです。

実は施設を案内してくださった太田さんと下田参事は、共に大学は農学部出身で現在は農業振興係。環境負荷の低減や、廃棄物削減のことも大切ではありますが、それまで「役に立たない厄介者」扱いされていた”し尿”を「資源」として見直し、その有効活用によって町の農業を発展させるという視点こそが取り組みが成功している最大の理由でした。
農作業の一部を町が担ってくれる!

先ほどお話ししたように、築上町は液肥を作るだけでなく、なんとその液肥の散布作業自体も行ってくれるんです。
田畑全体に肥料を散布するのは、楽な作業ではありません。また、農家さんの中にはご高齢な方も多く、作業を町が担ってくれるのは嬉しいことばかり。

立ち上げ当初、町がし尿処理施設と液肥製造施設を比較してコストを考える際に、「液肥散布作業」の項目まで考えていたそうです。農家さんに使ってもらうには、と考えられていたことがよく伝わってきました。
町全体で取り組むという意識
もうひとつの問題は、肥料の原材料として「し尿を使っていることへのイメージの悪さ」です。
「排泄物を人が食べる作物の肥料に使うって、衛生的に大丈夫なのかな?」という意見はやはりとても多かったそう。

元々江戸時代の農業においては、し尿は大切な資源で、それを肥料として散布することはごく普通のことでした。築上町で行っている液肥利用も仕組みは同じです。
しかし江戸時代とは異なり、現代の化学技術の進歩により、し尿を発酵熱で高温(50℃以上)に保つことで、大腸菌や寄生虫の卵などは死滅させることができるようになりました。そのため、より安心・安全な肥料を作ることができるようになっています。
築上町の取り組みを続けるには、町の人の理解が不可欠。

地域の学校では、町の循環型農業について学んだり、実際に液肥を使っている田んぼで田植えをしたり、自分自身も農業を支える一人だと学ぶ機会を多く作っているそうです。

太田さんや下田参事は、「子どもたちが学ぶと、家庭でその話をするんですよね。子どもたちに知ってもらうことで、親世代の理解も深まった気がします」とおっしゃっていました。
液肥を使った築上町の作物

田畑が多く、中でも稲や麦の栽培が多くを占める築上町。
菜種、スイートコーン、お米、大豆、レタスやブロッコリーなど、一年を通して、循環型農業で生産される様々な作物があります。
地元特産品|シャンシャン米“環”(たまき)

日本初!濃縮施設で、液肥をもっと幅広い作物に!

し尿から作られた液肥は、サラサラの液体にまで分解されているわけではありません。人が食べた野菜などの繊維分が残っています。
田んぼや畑に撒く場合は問題ないのですが、ビニールハウスなどの施設園芸では、液肥を通すホース内に詰まってしまい使用できないという難点があります。

しかし、その難点を解決する施設が築上町に新たに完成。
固形物を除去、電気透析をして肥料成分を濃縮削除することで、施設園芸にも利用可能な新たな肥料を九州大学の特許を利用して作りました。

施設園芸では、いちごの栽培が1番多い築上町。現在いちご農家さんや大学とも協力しながら化学肥料と比較した販売試験なども行っているそうです。
この施設は現在、日本で唯一!
今後の農業の発展に大きな一歩を踏み出した町として、ますます期待大です。
地道な取り組みで循環型農業を成功させた築上町
これまで様々なところに取材に行った中で、農家を含め町の事業者と行政が密に取り組む事業の難しさを多く感じてきました。
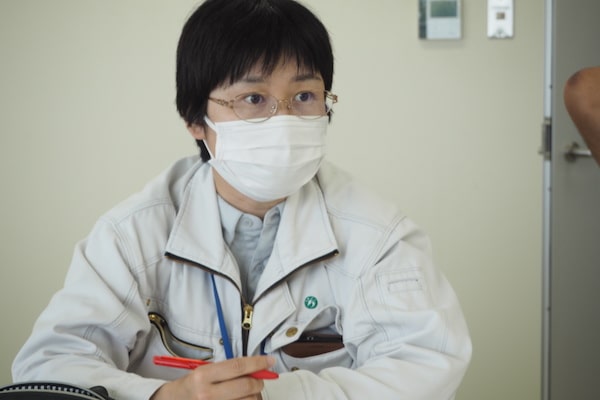
農家さんにとってという視点が終始ブレない説明に「すごいですね!」と驚きつつ興奮した私でしたが「そう!めっちゃすごいんですよー!」と私を超えて興奮気味の太田さん(笑)
築上町のこの仕組みが出来上がるまでに、取材では聞くことができなかった問題も多くあったことでしょう。それでも、ここまでの形ができたのは、下田参事を始め太田さんや歴代の担当者の皆さんが、農家さんや住民の視点を一生懸命に考えてきた結果だと思いました。

そんな小さな積み重ねの結果が、環境負荷の低減、廃棄物削減、さらに農家さんや消費者・子どもたちのためにもなっているんですね。
この記事を読んでくださっているあなたも、まず出来る小さな取り組みの一つとして、循環型農業で育った作物を選んで買ってみてはいかがでしょうか。
築上町で育った特産物が買える!メタセの杜

住所:〒829-0107 福岡県築上郡築上町弓の師765
築上町有機液肥製造施設インフォメーション
▼お問い合わせや見学のお申し込みはこちらまで
住所:福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2
電話:0930-56-0300(産業課 農業振興係)











